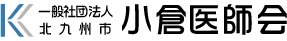小倉医師会の案内
事業計画
令和7年度北九州市小倉医師会事業計画
COVID-19も2類感染症から5類感染症に引き下げられ街行く人々にもマスクを着用しているものもずいぶんと数が減ってきており、一時期の混乱からかなり平穏を取り戻しつつある。COVID-19も時々のピークを認めるものも、その症状はかなり軽いものとなってきている。
さて、本年度の事業計画であるが、北九州市小倉医師会は地域保健課・臨床検査課・高齢社会事業課・看護専門学校の4事業部門の安定的な運営を図ることが重要と考える。昨年度は診療報酬、介護報酬、障害福祉サービスなどの報酬の同時3改定が行われており、どれをとっても蓋をあけてみれば減額改定となっており、医療を取り巻く環境は日々厳しいものとなってきている。
このような状況においても小倉医師会の総務部門、事業部門ともに職員と担当役員の努力により業務はかなり改善してきている。
地域保健課については特定健診、特定保健指導、事業所健診、学校検診、住民健診など各種検診業務を展開している。しかしCOVID-19がかなり平穏をとりもどしたとはいえ健診者数は大きく減少し、ようやく住民健診などの健診業務が増えてきているとはいえ散々たる影響を受けた。コロナ禍の影響は計り知れなく大きなもので、すぐに回復する状況には程遠い。職員一丸となって工夫に取り組んでいるが、なかなか難しい状態である。
臨床検査課については、会員医療機関の基幹業務である各種検体検査を受託して精度の高い検査を実施することで病院、診療所から高い評価を得ている。しかしここにもCOVID-19のため、我々会員医療機関における受診患者は激減し、そのため各種検体検査も激減した。それともう一つ大きな問題として電子カルテの普及である。新規開業の会員はほぼ100%導入しており、データの送受信に対して大きなコストがかかるため医師会検査センター離れを起こしており、これは今後も続くものと思われる。また、新規会員は開業コンサルタントとの契約により、入会時にはすでに電子カルテ業者や民間検査センターと契約が終了していることが多く、なかなか医師会検査センターを利用してもらえる機会が減っている。対策として、入会説明時に医師会検査センターを利用することを強く勧めているものの、改善には程遠い状況である。何の手も打たずにこのまま事業を進めれば、いずれ不採算事業に転落すると思われる。そこで昨年福岡市医師会にならい、大手検査機関と事業を提携し業務を開始した。まだ、目立った業績の改善は認めていないがいずれは医師会事業の中核を担うことが出来ると期待している。
高齢社会事業課は、国立病院機構小倉医療センターの敷地内に新築移転して早くも10年目になる。小倉医師会介護サービス総合センターと銘打ち活動している。国が推進する地域包括ケアの推進拠点として在宅医療・介護連携支援センターとしての重要な役割を持ち、 北九州医療圏唯一のデイホスピス事業を展開している。小倉医師会介護サービス総合センター内の研修室では、日々介護サービスを支える多職種に対する講演会や研修会を開催し、将来の介護関連職種の技術の研鑽に力を注いでいる。昨年度より始まった、第8次保健医療計画、第10次高齢者保健福祉計画や2025年問題もあり今後一番に医師会事業で活躍していただきたい事業課で期待されている。
北九州小倉看護専門学校は大正10年6月に開校され令和7年6月で104周年を迎える。令和4年10月に規模は縮小したが創立100周年記念事業を施行することができた。当校の最近の問題点として、准看護師科学生の受験希望者が年々減少してきており、ここ3~4年は入学定員を大きく割ってきていることである。このことは当校だけの問題ではなく近隣の医師会立看護学校も同様で、准看護師科の閉校を決めたところが続出している。当校も例外でなく小倉医師会の他事業との影響もあり昨年度閉校を決定した。ただ閉校を決めてもすぐに学生の募集を中止することは出来ず、本年度准看護師科の最後の入学生を迎え、4年後閉校となる。
100年以上の歴史と伝統ある北九州小倉看護専門学校を閉校する事はとても大きな決断で悲しいことであるが、他の小倉医師会事業の存続のためにはいたしかたないことである。
もう一つ会員の皆様にお願いがある。かなり疲弊した小倉医師会が立ち直るまで、昨年小倉医師会会費の増額をお願いした。北九州市内の5医師会の中でも小倉医師会会費は、事業を行っているためにかなり低額に抑えられている。しかし、このような事業低迷の状況の中、他医師会並みとは言わないが多少の増額をお願いしたい。小倉医師会の役員、職員も工夫を凝らしてがんばっている。何卒この件はよろしくお願いしたい。
小倉医師会の諸事業や行政委託の諸事業もいずれも会員の先生方のご協力のもとに運営されており、ご協力が得られなければすぐに頓挫してしまう。会員諸兄諸姉も大変な時期だとは思われるが、今後も皆様のご支援ご協力を切にお願いしたい。
令和7年度 小倉医師会事業内容
Ⅰ.上部医師会への提言
Ⅱ.医師会組織の強化
1.新入会員の指導充実
2.隣組組織の調整と連携
3.専門医会との連携
4.勤務医部会との連携
5.私的病院会との連携
6.専門医会相互の連携
7.歯科医師会と薬剤師会との連携
8.小倉医師会医療フォーラム - 次世代を担う人材の育成
Ⅲ.会員支援対策
1.小倉医師会無料職業紹介所の活用
2.医療情報システム等の活用
3.医業経営支援(税務・労務・医師信用組合の利用促進)
4.新入会員の支援強化
ア A会員(開業医等)
イ B会員(勤務医)
ウ C会員(臨床研修医)
5.広報機能の強化(会誌の充実と市民向け広報等)
6.医事調停への対応
7.労働保険事務組合の運営
8.研修医に対する医師会活動の説明
9.開業支援
Ⅳ.ITコンテンツの利用促進
1.会員・市民向け医師会ホームページの充実
2.医療機関検索システムの活用
3.講演会等のビデオ配信
4.「とびうめ@きたきゅう」及び「とびうめネット」の推進
5.医療DXへの取り組み ⅩⅢ.ITコンテンツの利用促進から移動
Ⅴ.医療安全対策の推進
1.医療安全対策シンポジウム・講演会の充実
2.医道倫理の高揚と医療安全情報の提供
3.医療事故防止対策
Ⅵ.生涯教育の充実
1.学術講演・研修会の開催
2.生涯教育講座の受講促進
3.ビデオ配信、e- Learning等のITコンテンツ活用
Ⅶ.医療保険対策
1.迅速な医療保険関連情報の提供
2.保険研修委員会・保険個別研修の開催
3.社会保険諸指導への協力
4.労災自賠医療情報の伝達と会員からの相談窓口業務
Ⅷ.地域保健事業
1.健診センターにおける特定健診・特定保健指導事業
2.市民への各種健診活動とがん検診フェアの開催
3.地域に密着した健康づくり
4.予防接種対策
5.学校保健対策(学校医会・園医会の充実)
6.産業医会・産業保健活動の強化と地域産業保健センターの利用促進
7.会員健診・従業員健診等の実施
8.働き方改革関連法案に関して中小事業所への協力
Ⅸ.臨床検査事業
1.検査センターのサービス充実と利用促進
2.精度管理の徹底
3.特定健診の業務支援
4.各種公的疫学調査への協力
5.検査データ通信の利用促進
6.検査室などの作業環境整備
7.使用機器の耐用調査と計画的運用
8.業務委託先との連携強化
Ⅹ.高齢社会事業
1.在宅医療福祉ネットワークの推進
2.介護サービス事業による在宅高齢者ケアの支援
3.地域における訪問看護師、介護支援専門員、介護職の研修充実
4.在宅医療・介護連携支援センターの支援と地域包括支援センターとの連携
5.デイホスピス事業の推進
6.小倉介護サービス事業者連絡会の運営への協力
7.認知症高齢者支援体制の推進
8.多職種連携の推進
ⅩⅠ.北九州小倉看護専門学校の運営
1.地域医療を支え、会員医療機関のニーズに応える質の高い看護職養成
2.e- Learning、iPad等を活用した看護教育の充実
3.准看護師科・看護師科の一体的運営
4.医師会立看護師等養成所間におけるICTを活用した授業の共有化への取り組み
ⅩⅡ.包括的地域ケアの推進
1.地域医療連携会議の活用
ア 病病連携・病診連携・診診連携の強化
イ コアメンバー会議の開催
ウ 地域医療連携パスの推進
2.地域医療支援病院運営委員会への提言
3.地域医療構想調整会議への提言
4.保健・医療・福祉・地域推進協活動の充実
ア 部会活動(高齢者支援・子育て支援・健康づくり)
イ 実務者勉強会「あい愛ネット」「ほっとスクラム」
ウ 健康づくり事業等の市民センターを中心とした地域活動
エ 三師会及び医療関係団体の連携推進
5.南北行政との連携強化
6.精神保健対策(アルコール・ニコチン・麻薬を含めた薬物依存症対策)
7.介護保険・障害者施策への協力
8.救急医療・防災事業への協力
ⅩⅢ.その他