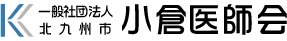おしらせ
「旧優性保護法に基づく優性手術を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」周知のためのリーフレットについて
★ 「旧優性保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する補償金等の支給等に関する法律」の施行等について(R7.2)
・旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ(子供家庭庁HP)
★ 「旧優性保護法に基づく優性手術を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」周知のためのリーフレットについて(R6.8)
・こども家庭庁リーフレット こども家庭庁HP (R6.8)
★ 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律周知のためのリーフレット等について(R6.4)
標記の件につきまして、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」(以下、「法」という。)が平成31年4月施行され、今般、本制度の周知を図るために作成されたリーフレットについて、下記のとおり記載内容が一部変更された旨、福岡県保健医療介護部より上部医師会を通じ通知がありましたのでお知らせ致します。
また、厚生労働省より、法に係る診断書は請求者にとって利便のよい医療機関やかかりつけ医が作成することが想定されることから、「医師のみなさまへのお願い」として診断書記載の手引きが作成されておりますので、併せてお知らせ致します。
記
1.医師の診断書に係る記載について
法に基づく一時金の支給に係る請求については、原則として、「生殖を不能にする手術もしくは放射線照射を
受けたことによるものである
可能性がある所見が現存しているかどうか」を医師に客観的に確認していただいた診断書が必要となります。
この診断書は、厚生労働省に設置される「旧優生保護法一時金認定審査会」が一時金の支給認定の判断をす
る際に参考とする資料であり、この診断書をもって、請求者が優生手術を受けたこと、もしくは受けていないことを
確定するものではありません。
したがって、手術痕が無い場合は無い旨を御記載いただき、手術痕の存在が確認できる場合は、当該手術痕が
優生手術によるものかどうか判断がつかない場合であっても、現認できる手術痕について記載した上で、診断書の
備考欄に何の手術によるものか判断できない旨を御記載願います。
なお、従前のリーフレットにおいては、請求に必要な診断書について「請求者が当時優生手術を受けたことを証
明する診断書」と受け取れる内容になっていたため、記載内容を修正しております。
2.電話での相談が難しい人への配慮について
電話での相談が難しい方に配慮し、リーフレットに本県相談窓口のFAX番号及びメールアドレスを追記したもの。
≪参考資料≫
・旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ 厚労省ホームページ
~旧優生保護法一時金支給請求に係る診断書の作成に当たって~
・「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する 一時金の支給等に関する法律 」に基づく一時金の請求等に関する事務の取扱いについて (厚労省) H31.4.24