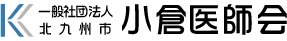おしらせ
令和6年能登半島地震について
★ 令和6年能登半島地震について(R7.10)
・令和6年能登半島地震による被災に伴う保険診療の特例措置の期間延長等について(R7.9.25)
・令和6年能登半島地震に伴う災害の被災者に係る保険医療機関等における一部負担金等の取扱いについて
・その14:R6.12.25
・その12:R6.11.12 ・その 13:R6.12.13
・医療機関・薬局等の皆様へ(R6.12.25 更新)
患者向けリーフレット【新潟県】 ・ 【富山県】 ・ 【石川県】 ・ 【福井県】
・令和6年能登半島地震による被災に伴う保険診療関係等の特例措置の期間の延長について(R6.11.12)
・令和6年能登半島地震に伴う災害の被災者に係る保険医療機関等における一部負担金等の取扱いについて
・令和6年能登半島地震による被災者に伴う保険診療関係等の特例措置の期間について(R6.9.18)
※ 令和6年能登半島地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて(R6.1.2)
・令和6年能登半島地震への医療支援に向けた支援金について(御礼)日本医師会
★ 令和6年能登半島豪雨に対する医療支援について(お礼)(R6.10)
★ 令和6年7月9日からの大雨による災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について(R6.7)
・令和6年7月9日からの大雨による災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について(R6.7.10)
【参考資料】暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いについて(H25.1.24)
★ 能登半島地震に関する動画について(R6.4)
・各動画タイトル
第1弾「能登半島地震 発災から1カ月が経過して」
第2弾「能登半島地震 特別対談」
第3弾「令和 6 年能登半島地震に関する日本医師会・4県医師会特別座談会」
長 編「能登半島地震における日本医師会災害医療チームの活動」
短 編「能登半島地震における日本医師会災害医療チームの活動」
★ 令和6年能登半島地震にかかる災害による被災に関する診療報酬等の請求の取扱いについて(R6.2)
・令和6年能登半島地震にかかる災害による被災に関する診療報酬等の請求の取扱いについて
(令和6年1月診療分)(R6.2.2)
・令和6年能登半島地震に伴う診療録等の文書の保存に係る取扱いについて(R6.1.18)
※(別添)文書保存に係る取扱いについて(医療分野)(H23.3.31)
・令和6年能登半島地震の被災に伴う労災診療費等の請求の取扱いについて(R6.1.5)
・令和6年能登半島地震にかかる災害による被災に関する診療報酬等の請求の取扱いについて(R6.1.4)
・(その2)(R6.1.7) ・(その3)(R6.1.12)
(参考)令和6年能登半島地震におけるオンライン診療を実施するための研修受講の取扱いについて(R6.1.12)
★ 令和6年能登半島地震による災害に係る介護報酬等の取扱いについて(R6.1)
・令和6年能登半島地震による災害に係る介護報酬等の取扱いについて(R6.1.2)
★ 令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について(R6.5)
・令和6年能登半島地震に伴う災害の被災者に係る一部負担金等の取扱いに関するQ&Aについて(R6.1.23)
・令和6年能登半島地震に伴う災害の被災者に係る保険医療機関等における一部負担金等の
取扱いについて(R6.1.11)
・(その2)(R6.1.12) ・(その3)(R6.1.15) ・(その4)(R6.1.17)
・(その5)(R6.1.22) ・(その6)(R6.1.25) ・(その7)(R6.2.2)
・(その8)(R6.3.1) ・(その9)(R6.5.13)
・令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて(R6.1.1)
・(その2)(R6.1.18)
医療機関・薬局等の皆様へ(R6.2.29 更新)
患者向けリーフレット【新潟県】 ・ 【富山県】 ・【石川県】 ・【福井県】
・令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について(R6.1.1)
(別添)暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いについて(平成25年1月24日付事務連絡))
(適用報)令和6年能登半島地震にかかる災害救助法の適用について【第1報】)
★ 動画「能登半島地震―発生から1ヶ月が経過して」のご案内(R6.2)
【 こちら 】よりご視聴可能です
★ 労働基準法関係
・令和6年能登半島地震に関するQ&A(労働基準法第 33 条第1項関係)(R6.1.12更新)
※ 厚労省通知・事務連絡(医療・介護・福祉・雇用・労働・年金他)
★ 令和5年石川県能登地方を震源とする地震にかかる災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について(R5.5)
・令和5年石川県能登地方を震源とする地震にかかる災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について(R5.5.5)
★ 平成30 年大阪府北部を震源とする地震による被災者に係る被保険者証等の提示等及び公費負担医療の取扱いについて(H30.7)
平成30年大阪府北部を震源とする地震による被災に伴い、被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、医療機関を受診した際に提示できない場合等も考えられることから、この場合においては、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)の他、被用者保険の被保険者にあっては事業所名を、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて組合名)を申し立てることにより、保険診療を受けることが可能な取扱いとする旨、 添付資料1 のとおり厚生労働省保険局医療課より事務連絡が発出されました。
また、公費負担医療の対象者であって、医療券等の関係書類等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していること等の場合には、各制度について、当面 添付資料2別紙1 のとおり、被爆者健康手帳や患者票等がなくても、①別紙の各制度の対象者であることを申し出、②氏名、③生年月日、④住所等を確認することにより受診できることが可能であり、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとすることが厚生労働省より通知された旨、福岡県保健医療介護部がん感染症疾病対策課及び日本医師会より通知があっております。
なお
1)当該被災者に係る診療報酬等の請求の取扱いについては、平成25年1月24日付け保険局医療課事務連絡
「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いについて」(添付資料1別添)に準じた取扱いであり、公費負担
医療の請求等の取扱いについては、 添付資料2別紙2 のとおりとされておりますのでご留意ください。
2)これらに加えて、当該災害による被災世帯の健康保険被保険者(被扶養者を含む)、国民健康保険被保険者
及び後期高齢者医療の被保険者に係る一部負担金の徴収猶予及び減免、保険料(税)の納期限の延長及び
猶予等の取扱いについては、 添付資料3~5 のとおり、平成25年5月に発出された事務連絡に準じた取扱いで
あることを申し添えます。
≪参考資料≫
・平成30 年大阪府北部を震源とする地震による被災者に係る被保険者証等の提示等について (厚労省) H30.6.18
・平成30 年大阪府北部を震源とする地震による被災者の「公害健康被害の補償等に関する法律」「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」「石綿による健康被害の救済に関する法律」等に係る公費負担医療等の取扱いについて (環境省) H30.6.22
★ 平成28年鳥取県中部地震による被災者に係る被保険者証等の提示及び公費負担医療の取扱いについて
平成28年鳥取県中部地震による被災に伴い、被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、医療機関を受診した際に提示できない場合等も考えられることから、この場合においては、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)の他、被用者保険の被保険者にあっては事業所名を、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて組合名)を申し立てることにより、保険診療を受けることが可能な取扱いとする旨、添付資料のとおり厚生労働省保険局医療課より事務連絡が発出され旨、日本医師会を通じて連絡がありました。
なお、当該被災者に係る診療報酬等の請求の取扱いについては、平成25年1月24日付け保険局医療課事務連絡「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いについて」に準じた取扱いですので、ご留意くださいますようお願いいたします。
また、公費負担医療の対象者であって、医療券等の関係書類を消失あるいは家庭に残したまま避難している等の場合には、各制度について、添付資料のとおり、被爆者健康手帳や患者票等がなくても、①別紙の各制度の対象者であることの申し出、②氏名、③生年月日、④住所等を確認することにより受診することが可能であり、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとする事務連絡が、厚生労働省関係当局より発出されております。